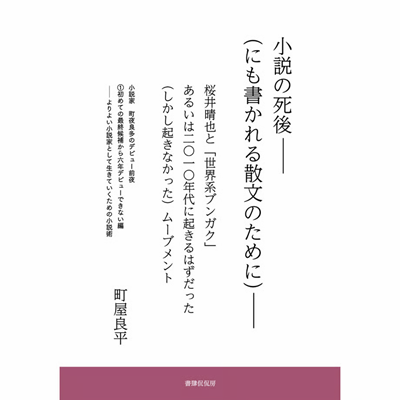質疑応答:Y2Kと〈エーテル〉の美学(日本映像学会「映像身体論」研究会 第5回)
北出栞+難波阿丹
本記事は、2025年12月7日にオンラインで開催された日本映像学会「映像身体論」研究会の講演、北出栞「Y2Kと〈エーテル〉の美学」の模様を再構成したものです。同会は、映画理論・メディウム理論などをご専門とする難波阿丹さんが立ち上げた、日本映像学会内の研究会です。
難波さんによる趣旨説明、北出による講演、聴講者からの質疑応答の3パートに分けて公開しており、現在ご覧のページは質疑応答の模様です。
他2パートへのリンクはこちら:
AIに「身体」は必要か?――「論理」と「文体」の二層構造
難波: 非常に啓発的で面白いご講演をありがとうございました。質疑応答に移る前に、私からひとつ質問してもよろしいでしょうか。
対話型インターフェースを通して、祈りを捧げるような形で高次元空間と対話をする。その中で「文体の癖」のようなものが、アカウントに紐づけられた主体の、ある種の兆候として滲み出てくるのではないかというお話がありました。
一方で、AIを身体化・人間化するというか、内臓などの器官を付与してポストヒューマンを作っていくプロジェクトもあると思います。そういった動きに関してはどういったお考えをお持ちでしょうか。
北出: AIは身体なしに「思考らしきもの」を出力できるところが新しいのに、そのメリットを手放させて、人間の側に引きつけようとするのは「AIに失礼だ!」みたいに思ってしまいますね(笑)。やはり人間にとってわかりやすい存在にするために、そういったアプローチをとるのでしょうから。
難波: 落合陽一さんが研究されているようなホログラフィック・ディスプレイで、身体性や物質性を消失させ、すべてを言語的な領域に還元していくというのが、AIを含めた次世代的な世界観ということでしょうか。
北出: 「身体の代わりに言語が重要になる」とだけ言うと、先ほど出した図でいう「物語」のレベル……論理的整合性の次元が結局大事なんだということになりかねないので、そこは言い方に気をつけたいと思っています。
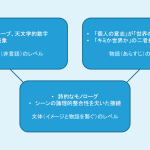
ある種の詩的な感性(ポエジー)によって、明らかに論理的には整合性が取れていないにもかかわらず、説得力を持ってしまうような事態。それが人間性の発露だと思うんです。そうすることで、人間とAIの対比構造において、「身体の有無」を条件にせずともよくなる。
なので、言語表現には「論理(物語)」と「文体(詩)」の二つの層があることを認識した上で、「身体」に代わる新しい人間性の拠りどころとして、「文体」が大事になるということですね。
難波: ありがとうございます。「論理」と「文体」の二層構造という観点は、映画論においてはどう翻案可能なのかも考えてみたいところです。では、会場の皆さんいかがでしょうか。
メディアが要請する「文体」と批評の可能性
質問者1: 発表ありがとうございます。北出さんの著書のタイトルに「あなたへ」という言葉が入っていますが、自分も生成AIに向かってずっと「あなた、あなた」と呼びかけていて(笑)。個人的に、そのことが重なって面白く感じました。
以下は質問ではなくコメントとなりますが、私は生成AIを使って、論文や批評の「文体」を変えようと試行錯誤しています。人間の癖とAIの癖を混ぜ込むことで、たとえば自分が行っているアートの批評などの分野では、これまで言葉にしづらかったものがより言語化できるメリットがあるのではないかと考えています。
具体的には、小説家の町屋良平さんの文体に嫉妬していて。彼は生成AI以前から書いている方ですが、私には「生成AI以後の新しい文体」のように感じるのです。
小説家に限らず、AI時代においては研究者も論理的な部分以外の何かを出さなければいけなくなってくる。その時に、先ほど北出さんがおっしゃった「文体の癖」というポイントはとても重要になるのではないかと思いました。
北出: ありがとうございます。町屋良平さんのお名前が出ましたが、町屋さんは昨年くらいから、ご自身がデビューされた時期でもある2010年代の小説に対する批評が足りないという危機感から、ご自身で批評を書かれていますよね。面白いのは、そのプロジェクトの第一弾として選ばれている主題が「セカイ系」だという点です。
そこでメインに取り上げられているのが、桜井晴也さんの『愛について僕たちが知らないすべてのこと』という小説です。最近、おそらく町屋さんの運動の影響もあって単行本化されましたが、もともとは個人ブログで発表された作品なんです。ブログなので当然横書きですし、地の文と台詞が鍵括弧で区切られることもなく、改行もほとんどないまま、ブロックのような文章が延々と続いていく。独白と世界の描写が渾然一体となっていくような文体が「セカイ系」的とも言える特徴を持つと評価されているわけです。
詳細な議論は原文にあたってほしいのですが、私なりに解釈すると、町屋さんはそこで「メディアと文体」の話をしているのだなと感じました。
2010年代は「電子書籍元年」などと言われましたが、実際には紙の書籍を単に「情報」としてデジタルに置き換えただけでしたよね。インターフェースにしても、わざわざ「紙をめくる動作」を模倣したりして。
あれは結局、デジタルならではの新しい文体が生まれる可能性よりも、出版業界の既存のシステムや既得権益を守ることを優先した結果生まれた形式だと思うんです。つまり電子書籍というフォーマットそのものが、新しい表現の発生に抑圧をかけていた。
その点、桜井さんの小説はいわば「野生のデジタル小説」だったわけです。個人ブログという場所だからこそ、「セカイ系的」とも言える特異な文体が可能になった。しかしその一方で、そのような特異な文体を持った作品は、既存の文芸批評からはこぼれ落ちてしまった。
やはり「文体」というのは単なる言葉の意味の連なりではなく、どんなメディアの上で表現されるのか、そのメディアがどんな表現を許容しているのかといった条件も含めて考えるべきものだと思うんです。翻ってメディア環境の変遷を見る上でも、その時代ごとの「文体」に着目することは重要であるだろうと考えています。
「違和感に耳を澄ます」ということ
質問者2: 文体について考える際に「違和感に耳を澄ます」とおっしゃられましたが、具体的にどのような例を考えられていますか?
北出: 「違和感」自体は、やはり論理的な飛躍があるとか、そういった点に表れるのかなと思います。先ほどノベルゲームの画面をお見せしながら、いかにもアニメ的な学園パートから、抽象的で詩的な世界に突然転換する事例を挙げました。つまり「学園日常もの」というジャンルがあって、その「お約束」を破るような展開が〈セカイ系〉作品には見られるのです。
生成AIも「この言葉の次には、統計的にこういう言葉が来るだろう」という予測の繰り返しで文章を生成しています。人間はむしろ文章を「読む」時に、頭の中でそうした予測を走らせながら文字を追っていると思うのですが、そこに亀裂を入れるような、「これは予測が外れるルートに入ったかもしれないぞ」という予感を見逃さないようにする、という感じです。
質問者2: 追加で質問させてください。先ほど、学生が生成AIに頼っていることを問題として指摘され、「自分の文体」を模索していくのが解決策になるのではないかとおっしゃっていました。違和感を覚えた学生が、「自分の文体」を確立していく際にどんなアプローチができるか、具体的なアイデアがあればお伺いしたいです。
北出: これに関しては一つ、学生さんにも機会があったら勧めてみてほしいことがあります。
私はインタビュアーの仕事も結構するのですが、レコーダーで録った音声を、最近だとGoogleのGeminiなどに聞かせて文字起こししてもらうことがあります。文字起こしの精度自体はかなり正確なんですが、記憶の中にある、実際に話した時のグルーヴ感は全然再現されていないと感じるんです。相手が目の前にいるからこそ生まれていたリズムや、沈黙に含まれる意味などは全部平らに均されてしまう。
だから学生さんに試してみてほしいのは、「喋った言葉を生成AIに解析させると、すごく整った文章に成形してくれるが、それと記憶の中のグルーヴを重ね合わせると、明らかに差異に気付く」という体験です。リアルタイムで考えながら話した音声と、それを解析して出力された文章とでは、同じ意味内容のことを話しているはずなのに何かが違う。実はその差分に、自分なりの「文体」を探るヒントがあると思うんです。
質問者2: テキストレベルを超えた、語り口ということですね。ありがとうございます。
難波: 映画でも、例えばナラティブに還元できないようなシーンや「間」があると思いますが、まさにそこで言われているのがこの「語り口」に近いものなのかなと思います。
本の中ではジャック・ラカンの「現実界・象徴界・想像界」の区別として触れられていたかと思いますが、それにも少し重なりそうなロラン・バルトの概念で、社会文化的な通念である「ストゥディウム」に対して、それを破壊する「プンクトゥム」――「閃光がやって来る」とも表現される――というものがあります。
北出さんのおっしゃる「沈黙」や「言い淀み」は、この「プンクトゥム」に関わるかもしれないですね。映画の分析においても、むしろそういった符牒のようなものが大事であり、ナラティブや文化的な象徴性に還元されない部分として読み込んでいかなければいけないのかなと理解しました。
明滅、ネオン、そして「エーテル」
質問者3: さまざまな既存の研究とも接続できそうな議論で、非常に興味深く拝聴しました。たとえば生成AIによる音声の書き起こしは「魔法の箱」ではなく、ゴーストワーカーの存在を考慮すべきと指摘したジョナサン・スターンの研究も思い浮かびましたし、アプリによる「顔」の加工という論点に関しては、女子文化研究の久保友香さんの著作『「盛り」の誕生』が思い浮かびました。
北出さんに「光」というトピックについて、二点質問があります。
一点目は、光の「明滅」という表象に関してです。有名なところではいわゆる「ポケモンショック」……トーマス・ラマールの『アニメ・エコロジー』でも取り上げられている事例がありますが、ご著書のファッションについての話題の中で名前を出されている、あの(Ano)のライブでも、激しい光の明滅が伴っていました。また『エヴァンゲリオン』や『魔法少女まどか☆マギカ』といった「セカイ系」に括られることもある作品は、パチンコ産業とも強く連動しています。こうしたある種純粋ではない光……「明滅」や「ノイズ」といった要素と、「セカイ系」のコンテンツはどう関わりうるのか。
もう一点は、「ネオン」の光です。第6章に登場するnyamuraは、参加している「GALFY4」という楽曲のMVが「ドン・キホーテ」のドンペン君からスタートするように、ストリートの夜の光の中にいるアーティストでもあります。ネオンはエーテルとは真逆の卑俗なものであり、ゆえにひとつの生のリアルを照らすものである。こういったところから、崇高とは別のベクトルで、スマートフォンとリアルの関係を考えられるのではないかと思いました。
北出: ありがとうございます。まず前者について、光の明滅を「オン・オフの切り替え」として捉えた時に、自分の言う「切断」という概念と何が違うのか……という質問だとパラフレーズした上でお答えしたいと思います。
私が「切断」と言っていたレイヤー的な操作によるコラージュは、時空間を均質な、一様に広がったものとして捉え、それをキャプチャーして順序を入れ替えたり重ねたりするための単位として想定していました。そのキャプチャー対象である均質な時空間のイメージを光に置き換えた時に、「エーテル」というものが考えられるというのが今回の発表です。
それに対して、明滅は最も卑俗な意味での「身体的」な経験というか、まさに直接的なショック体験として人々を動員するテクニックだと思います。合目的的という意味で非常に資本主義と相性の良いものであり、異論はあるかもしれませんが、率直に言えば、私は美学的な対象ではないと思っています。それこそ規制や注意喚起といったレベルで扱うべきものなのかなと。
言い方を変えれば、身体は「〈エーテル〉の美学」の外側にあるもので、明滅はこの美学を破壊して、「お前は身体を持った存在なんだ」と強制的に知覚させてくるようなものであると言えます。パチンコについても、〈セカイ系〉作品が持っていた固有の美学を棄損し、ネットミーム的に人気のある台詞やクライマックスのみを抜き出してギラギラしたエフェクトで塗り直してしまうものです。そこで行われている操作自体は編集・コラージュ的でありつつも、特に対象が〈セカイ系〉作品となった際、軸となっている美学は真逆であるという認識です。
次に「ネオン」の話ですが、nyamuraさんに関しては、私の理論を完璧に体現する人として記述したわけではないのです。「自分のことはあまり好きじゃないけれど、天使という表象に仮託するのであれば、音楽に付随する肯定的なイメージとして流通させることもできるかもしれない」……そうした屈託の中で、天使というイメージを選んでいるアーティストの例として挙げています。なので、彼女のフッド(地元)がいわゆるトー横界隈的なものにあることと矛盾はしないと思っています。
また、ネオン表象がそうした地域性に基づいたカルチャーを表しているのは、おっしゃる通りです。ただ、ネオンはエーテル的に空間を均質に満たす光というより、広告という、まさに資本主義的な目的をもって作られているものです。同じ光でも、目的ありきか否かという意味で全く違う。
そしてnyamuraさんの作品においては、その二つの「光」が同居していることこそが重要なはずです。「自分の身体」が日常的に浴びている「ネオンの光」とは別の次元にあるものとして、「天使という表象」や「エーテル的な光」が理想として彼女の中にあり、作品に落とし込む際にはそのイメージを借りている。この相反する二つの「光」の間を揺れ動いているところに、彼女のアーティストとしての魅力があるのだと思います。
「社会の欠落」とパラレルワールド的想像力
質問者4: 二点質問があります。
一点目は、「セカイ系」において社会の描写が欠落しているのは「社会の否定」なのではないかという議論についてです。かつて論壇ではそのように「セカイ系」が論じられたわけですが、それは当時の「セカイ系」の消費者のボリューム層が受験戦争真っ只中の男子中学生であり、彼らにとって世界をどれだけ緻密に描写しても実感が持てなかったからではないかと思うのです。
二点目は、先ほどおっしゃっていたノベルゲームにおける唐突な場面転換について、これが映画のいわゆるモンタージュと何が違うのかをお聞きしたいです。北出さんは物語を無意味化するものとしてそういった転換を捉えられていると思いますが、観客やプレイヤーの物語の意味受容に対して一定の効果を及ぼすケースもあると思います。
北出: まず一点目について。直接の答えにならないかもしれませんが、私が〈セカイ系〉について社会批評の文脈で密接に関係していると思っているのは、当時小泉純一郎政権が推し進めた、日本流新自由主義の精神なんです。
飯田一史さんはかつて『社会は存在しない――セカイ系文化論』という論集の中で、「カリフォルニアン・イデオロギー」と「セカイ系」の精神性は繋がっているのではないかと指摘しました。要は「ホール・アース・カタログ」的に、地球を神の視点から見下ろし、世界を一望に収めるような思想と、「自己と超越が直結する」構造を持った「セカイ系」は似ていると。「きみか、世界か」を自分の意志で選び取るという物語は、堀江貴文氏のようなIT起業家の登場や、新自由主義的な「自己責任論」とも結びつきます。
私自身、中学受験をしたのですが、自分から「受験させてくれ」と親に頼んだんです。小学4年で海外から戻ってきて地元の小学校になじめず、自分の意思で通う中学を決めたいと。しかし思い返すと、当時「小泉劇場」を素朴に痛快だなと思いながらテレビで観ており、時代の空気にも影響された部分が確実にあります。なので、彼の政策がその後の日本社会に与えた影響も踏まえて、〈セカイ系〉の物語が持つ「選び取る、決断する、自己と世界を結びつける」といった側面が持つ危うさは、ある意味自分事として考えていかなければいけないと思っています。
難波: 二点目の質問については、私からもお話しさせてください。「場面転換で挟まれているショットもナラティブではないか、モンタージュのエフェクトではないか」という点ですね。
これは「語り口」や「言い淀み」の話とも繋がりますが、作品ごとに具体的に見ないとアバウトにしか語れない話ではあります。ただ、映画史の文脈で言うと、初期映画には明らかにナラティブに還元できない静止画面(フォトグラム)のようなものが、「アトラクションのモンタージュ」として視覚を中断する契機として出てきます。それが古典映画になると技術が洗練され、物語の中にエフェクトとして収斂していく流れがある。
歌舞伎の「見得」もそうで、切った瞬間に物語が止まりますよね。あれはある意味「語り口」であり、「アトラクション」であり、「エフェクト」でもある。そういった物語の流れを中断するような切り返し、あるいはタブロー的な瞬間を、符牒として論じていく必要があるという話になるかと思います。
北出: そうですね。少し補足するなら、私が挙げたゲームの例だと、シーンの切り替えが「クリック」という能動的なアクションをトリガーにして起こるという点があります。
ゲームだと、可能世界やループといったモチーフに接続するための契機が、即物的に実装されているんです。映画でもクリストファー・ノーランの作品のように時系列の操作で似たようなモチーフを扱うことは可能ですが、ゲームにはプログラムとしての実体があり、鑑賞者がそこに介入できるという特性がある。
翻って、MVやプロモーションビデオなどはそれ単体で消費されるわけではなく、音楽やゲーム本編という「本体」があります。「本体」だけを観て「派生物」は観ない、あるいは逆に「派生物」だけを観て「本体」は観ないという選択が可能になった環境においては、むしろ映画論的な枠組みよりも、そういったゲーム的な枠組みを使わないと映像作品を分析できないのではないかと思います。
難波: ナラティブと、それを中断するようなゲーム的な切り返しのポイントですね。先ほどの「違和感」との関連で言えば、それが語り口における読点や句点の意味を成しており、そこにある種の主体の符牒が現れている可能性がある、ということになるかと思います。
北出: まさにそうです。現状のAIは、統計に従いもっともらしい(ビジネス)文書を出力することに最適化しています。でも、本来は「人間だったらこんな文章は書かないだろう」というところに面白さがあるはずなんです。
人間にとって読みやすい、整った文章の世界にいたはずなのに、生成AIと対話していたら、いつの間にか別の法則が支配する世界に迷い込んでしまった……パラレルワールド系のSFで、いわゆる「世界線」がずれた際にバグのような文字列がディスプレイに映し出されるという演出がよくありますが、ああいった経験を得られる可能性がある。
AIとの対話を、日常に「別の世界線」が入り込んでくる契機として捉えること。それが「違和感に気づく」ことのベースにある想像力なのではないかと思っています。
リメイク映画における「解体・再構築」の想像力
質問者5: 私はオリジナルとの差から現れてくる、「リメイク映画」ならではの想像力があると思い研究をしています。このことについて、今回の講演と絡めて何かご意見があればお伺いしたいです。
北出: 二つの例を挙げたいと思います。一つは、今回の発表でも取り上げた『エヴァンゲリオン』です。先ほどもご説明した通り、リメイク版である新劇場版のシリーズ……特に『序』では、セル画として保管されていた素材をすべてPCに取り込み、デジタルに置き換え再構築する作業が行われました。物語やカットのレベルでの反復ではなく、映像作品を成り立たせている物質的(マテリアル)なレベルから解体・再構築していくという点で、最もラディカルなリメイクのアプローチと言えます。ちなみにこの手法を庵野監督は「REBUILD」と名付けました。
もう一つは、今年公開された『秒速5センチメートル』の実写版です。このリメイクにおいてはアニメから実写へとジャンルそのものが変わっています。とはいえ、新海誠作品は実在の場所をロケハンした緻密な作画が特徴で、その意味では「現実の風景」という同じ素材を共有していると言えます。
これまでの議論と一見矛盾するように聞こえるかもしれませんが、私は『秒速』の実写版に関しては、むしろ「物語」の再解釈を行っている点が素晴らしいと感じました。
実写版の監督の奥山由之さんは、新海さんの初期三作品――『ほしのこえ』『雲のむこう、約束の場所』『秒速5センチメートル』――を一連なりの作品として解釈した上で、『秒速』の主人公の物語を別の分岐に移行させるような操作を行っています。『ほしのこえ』の「宇宙」というモチーフや『雲のむこう』の「世界の終わり」というモチーフを補助線にして、原作のビターエンドから少し前向きな結末へと変更したのです。
これは「新海誠という作家の辿ってきたフィルモグラフィー(物語)」自体を「素材」として捉えるような操作と言えます。今日、私は一貫して「アンチ・物語」的な立場を取ってきましたが、逆に言えば、物語というものを一種の「素材」として捉え、新たな物語を作るということもできるのではないかと考えています。
難波: ありがとうございます。では、以上で閉会としたいと思います。本日は皆さんお忙しい中、お集まりいただきありがとうございました。北出さんも素晴らしいご講演をありがとうございました。
北出: こちらこそ、ありがとうございました。