幾千億年の孤独――『ヘブンバーンズレッド』3周年特別ストーリーイベントに見る「世界の終わり」の想像力
北出栞
2025年2月2日、スマートフォン向けRPG『ヘブンバーンズレッド』にて、3周年特別ストーリーイベント「あの娘ぼくが唯一の光だと言ったらどんな顔するだろう」が配信された。本作の原案・メインシナリオに加え、挿入歌として流れる全ボーカル曲の作詞・作曲も手がけるゲームクリエイター、麻枝准による書き下ろしのシナリオとなっている。
本イベントは、麻枝准のルーツであるPCノベルゲームというメディアにおいて蓄積されてきた技巧やテーマ性を、スマートフォンゲームという現代のメディアに実装し直すことで、当該メディアそのものへの批評性を示すシナリオが白眉となっている。あくまで一ゲームタイトル内のシナリオでありながら、単独でも麻枝准というシナリオライターの「作品」として論じるに値する対象と感じ、このたび筆を執った次第である。
※本記事は『ヘブンバーンズレッド』当該イベントおよび、メインストーリーのネタバレを含みます。
「あの娘ぼくが唯一の光だと言ったらどんな顔するだろう」概要
本イベントは主人公・茅森月歌の所属する第31A部隊に、なぜか先輩兵士の白河ユイナが所属しているというシチュエーションから始まる。事前公開されたPVの中には「31Aは強くなった、白河のおかげで」とあり、これまでプレイヤーには開示されていなかった31Aと白河との秘話を明かすストーリーのような雰囲気を醸し出していた。
しかし実際にはそうではなかった。今回のイベントでプレイヤーが辿ってきた物語は、実はAIによるシミュレーションだったという真相が終盤で明らかになるのである。
一見突飛にも思えるこの真相の開示だが、人類の生存を脅かす地球外生命体「キャンサー」と、それと戦う「セラフ部隊」の活躍を描く『ヘブバン』の世界観においてはありうる話である。このAIは、セラフ部隊が拠点としている基地内のシステム(戦闘シミュレーターなど)に活用されていたもので、ずっと本作をプレイしてきた人にとってはある意味、実は最も身近にいた「キャラクター」でもある。
なぜAIが今回のようなシミュレーションをしていたのかというと、基地が無用のものとなった後、宇宙そのものが死滅するまでの、幾千億年の孤独に耐え続けるためであった。そう、今回のイベントは、2025年2月2日時点で未だ完結していない、メインストーリー終結後の時間軸を描いているのである。
人類とキャンサーの戦いがどのような結末を迎えたかは、このイベントからは窺い知れない。しかし、たとえ人類がキャンサーに勝利したとしても、あるいは敗北して人類は滅亡してしまったのだとしても、いずれにせよ遠い未来において地球という星は「終わる」のである。
今回の語り部たるAIは自己進化を続けて、宇宙そのものが消滅する幾千億年先まで生き続けなくてはならなくなってしまった。その間、ずっと自我を保ったまま、孤独に宇宙の行く末を観測し続けなければならないのは過酷すぎる。そんな永遠のような時間を過ごす慰めとして選択されたのが、AIから見ても一際目立つ人間だった茅森月歌という「主人公」の輝きを、彼女が最も憧れた存在である白河ユイナの視点から、逆照射的に見つめ直すという物語だったのである。

「キャラクターの真正性」をめぐる問いの多重化
本イベントはスマートフォンゲームというメディアの特性を生かしつつ、複数の論点において高度な批評性を有している。以下、順に見ていこう。
第一は、「虚構のキャラクターの存在論」という論点である。
そもそも、スマートフォンゲームにおけるキャラクターは、根本的な乖離を抱えている。物語における感情移入の対象であると同時に、ガチャというシステムを通じて排出され、特殊能力や属性、ステータスによって評価される「戦闘ユニット」でもあるのだ。この乖離は、シリアスな戦場に水着姿のユニットを編成できてしまうといった、ゲーム的な都合と物語的なリアリティの不協和として前面化する。「ガチャで手に入れたこのユニットは、本当に物語の中の〇〇(キャラクター名)なのか?」という問いは、スマートフォンゲームという形式に常につきまとうものである。
こうした問いは、過去の麻枝准/Key作品において、「ループ」や「記憶喪失」といった設定を用いつつ、倫理的な問題としてプレイヤーに突きつけられてきたものである。「無数に繰り返されるループの中の、AとA’は同一人物なのか」「記憶を失った恋人は、以前と同じ恋人と言えるのか」……目当ての結末にたどり着くべく、何度も物語を周回するプレイヤーの体験とリンクすることで、キャラクターを「コンテンツ」として消費するプレイヤー自身の罪悪感をも揺さぶる問いとして機能してきたのだ。
しかし、現実の開発スケジュールに沿って順次新たなストーリーが追加される運営型のスマートフォンゲームでは、こうした設定を導入することは難しい。そこで同様の問いをプレイヤーに突きつけるべく『ヘブバン』が採用したのが、プレイアブルキャラクターが、実はナービィという地球外生命体によるオリジナルの人間のコピー(ヒト・ナービィ)であるという設定だった。すべてのキャラクターは、はじめから「本当の〇〇(キャラクター名)」ではない。この設定により、ガチャから無数に排出される同一キャラクターや、季節外れの衣装といったゲーム的虚構性が部分的に正当化されているのである。
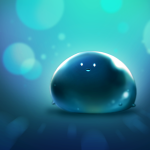
今回のイベントは、この構造をさらに多重化させている。語り部は白河ユイナの人格をシミュレートしたAIであり、その事実を知ったプレイヤーは彼女を「本物(本編の白河ユイナ)のコピー」として認識する。しかし、イベントが進み、担当声優・花守ゆみりの迫真の演技によってAI白河ユイナ固有の実存が確立されていくにつれ、プレイヤーは以下の事実に直面させられる。「確かにこの白河ユイナはAI(偽物)だが、そもそも私たちが「本物」と思って接してきた本編の白河ユイナも、かつて実在した人間の情報を写し取ったヒト・ナービィ(偽物)だったではないか」と。
「かつて生きていた人間(オリジナル)」の「コピー(ヒト・ナービィ)」の、さらなる「コピー(AI)」……「AI白河ユイナ」のこうした立ち位置は、安易な「本物/偽物」の二元論を無効化する。クライマックスでAI白河ユイナが発露する感情に心を動かされてしまった瞬間に、プレイヤーは「キャラクターの真正性を保証するのは、唯物論的なオリジナル性か、それともそこに宿る感情の強さか」という、麻枝准が長年問い続けてきたテーマを突きつけられることになる。それは、これまでガチャで引いてきたキャラクターに対するプレイヤーの向き合い方に、幾許かの変化をもたらすものでもあるだろう。
運営型スマートフォンゲームの「終わらなさ」に抗して
第二は、スマートフォンゲームもそうである「運営型」のタイトルをどのように「作品」として切り出せばよいのかという論点である。
本イベントの途中までの展開はメインストーリー第一章をなぞる形で進行し、「これは「ループもの」なのではないか?」とプレイヤーの予想を掻き立てた。その予想は終盤に「実はAIによるシミュレーションだった」という形で裏切られることになるわけだが、こうしたミスリードについては前例があった。
蒼井えりかという、メインストーリー第二章で退場してしまうキャラクターがいる。キャンサーとの戦いについて何かを知っているかのような素振りを見せ、ゲーム全体への導入となるメインストーリー第一章の冒頭では、入隊式に臨む茅森が見た白昼夢のような形で、彼女が死を迎えるまでの顛末が断片的な映像の連なりとして挿入される。そして第二章のラスト、蒼井は茅森たちをキャンサーの攻撃から守る形で、実際に命を落としてしまう。彼女自身のどこか憂いを帯びた雰囲気と、プロローグでのフラッシュバック的な演出から、プレイヤーは「ループ」展開を予想したのだ。
結論を言えば、蒼井がキャンサーとの戦いについて詳しかったのは、茅森たちの着任前から兵士だった……つまり前世代の生き残りだったという事情によるものでしかなかった。憂いを帯びて見えたのは、彼女が一度見た光景を完全に覚えてしまう「完全記憶能力」を有しており、かつての仲間たちが死にゆく中ひとり生き残ってしまったという、強いサバイバーズ・ギルトに苛まれていたからであった。
茅森が見た白昼夢は結局何だったのかという謎は依然として残るが、その内容が蒼井に関わる映像に偏っていたことに関しては――身も蓋もない話だが――当時メインストーリーは第二章までしか実装されておらず、使える映像素材がそこまでのものしかなかったという事情によるものでしかないだろう。少なくとも蒼井が、世界の構造に関わる重大な存在であることの根拠とはならない。

こうした前段があった上で、今回のイベントがある。白河ユイナは過去、彼女を中心とした複数のイベントにおいて「天啓」という未来予知のような能力を持つキャラクターとして描かれてきた。蒼井と異なり、明確に彼女自身に備わった能力を介して、世界のあり方そのものに干渉する様子が描かれてきたのだ。今回は「特別ストーリーイベント」と銘打たれたこともあり、白河ユイナは『ヘブバン』世界をループする特別な主体である――あるいは、それに類する「観測者」的な立ち位置の人物である――と明かされるのではないかと、プレイヤーに期待を抱かせることになったのである。
しかし先述の通り、本イベントで開示される真相は「ループ」でも「パラレルワールド」でもなく、「AIによるシミュレーション」というものだった。幾千億年先まで続くこのシミュレーションは、あくまで現在進行中のメインストーリーと同じ時間軸上において行われている。
蒼井のケースを経て、一度ならず二度までも「ループ」展開への予測が覆されたことは、何を意味するのだろうか。
運営型のスマートフォンゲームにおいて、物語の「終わり」を描くことは周到に避けられる。物語が「終わらない」限りは、ビジネスとして利益を上げ続けることができるからだ。それゆえに、イベントシナリオは往々にして「本編の幕間」や「ありえたかもしれないIF(パラレルワールド)」として処理される。
だが麻枝准は、本イベントでそうした定石から外れるようなシナリオを執筆した。AIが観測し続けていたのは可能性の分岐の先の「あり得るかもしれない終わり」ではなく、物理法則に従い宇宙が迎える「絶対的な終わり」である。人類がキャンサーに勝とうが負けようが、幾千億年後には銀河が衝突し、星は死に絶える。本イベントのシナリオは、スマートフォンゲーム特有の「引き伸ばされた現在」を置き去りにするように、時間軸を無限遠点まで一気に伸長させてみせたのである。
このAIの抱える幾千億年の孤独は、私たちが「終わりの見えない」スマートフォンゲームに向き合い続ける体験と重なっている。そこにイベントのクライマックスという形で区切りが入るのは、運営が続く限り「終わりの見えない」ゲームをプレイさせられ続ける私たちに対し、ひとつの「終わり」を垣間見せるものとして、ある種の救いを与えてくれる。同時に、たとえ最後までメインストーリーが描かれなかったとしても、この『ヘブバン』という宇宙は確かに存在していたのだと打ち立てる、ひとつの記念碑ともなっているだろう。
天文学的スケールの導入と「切断」的な文体
第三は、シナリオが扱う時間的なスケール感と、それを表現する文体の組み合わせの妙という論点である。
「今回の物語全体が、AIによるシミュレーションだった」という真相の種明かし部分にあたるAIのモノローグパートでは、「まず10億年が経ち、地球上の海が蒸発した。/30億年が経ち、灼熱の星と化した。/45億年が経った時、天の川銀河とアンドロメダ銀河が衝突した。/60億年が経ち、太陽は約150倍にまで膨れ上がり赤色巨星となった。/始まりがあったように終わりは訪れるだろう。計算上では2000億年後だ」……と、天文学的な数字が次々と列挙される。宇宙空間を描いた決して枚数が多いとは言えない静止画とともに、断片的にその推移は示されるのだ。

そもそも、このように時間をダイナミックに飛躍させる語り口は、PCノベルゲーム時代に麻枝が得意としてきたものである。それは当時のコンピュータの処理能力の限界から、必然的に要請された技巧でもあった。クリックに応じてスライドショー的に切り替わるイラストと、一度に最大でも三行しか表示できないテキストボックスという制約の下、緩慢な日常パートから唐突に、真っ白な背景に断片的なモノローグだけが表示される画面へと飛躍する。最初期の作品『ONE~輝く季節へ~』においては、それが「永遠の世界」という設定に落とし込まれていた。

麻枝作品における「時空間の飛躍」は設定のレベルだけでなく、テキストの文体にも及んでいる。本イベントで、白河ユイナが茅森に宇宙の話をするくだりがある。後に読み返すと、AIが実際にそういった宇宙の歴史を見届けてきたことの反映となっていることに気づかされるわけだが、最初は単なる雑談のような形で冒頭に提示される。
茅森:こんなところに突っ立って、何してるの、ユイナ先輩!
白河:ふっ…月歌か。光を見ていた。
茅森:光…? 太陽?
白河:いや、宇宙が始まった138億年前の光だ。
茅森:え、なにそれ!? 肉眼で見えるの!?
白河:見えるとも。人差し指と親指を1センチほど開いてみろ。
茅森:こうでありますか。
白河:そうだ。そこには宇宙の始まりから届いた138億年前の光の粒子が410個ある。
茅森:全然信じられないや…。
白河:ビッグバンによるものだ。そこから宇宙の時間は始まった。
茅森:それまでは時間はなかったの?
白河:そうだ。生きるということはそこから始まったとも言えるな。
茅森:すごい…それって奇跡的なことじゃない?
白河:そうだ。生きる喜びもそこから始まったとも言える。
茅森:やったね!
一見すると、単に論理的な整合性を欠いた会話のように見える。まず「宇宙の時間が始まる」ことと「生きることが始まる」ことの並置。ここで話題になっているのは物理学上の話なわけで、「時間」は客観的な計測概念として持ち出されているはずなのだが、そこに「生きる」という実存的なワードが唐突に接続される。さらにその後の「奇跡」と「生きる喜び」の連鎖、最後の「やったね!」という台詞に至るまで、随所に論理の飛躍を含んだテキストと言える。
しかし、これは麻枝准の作家性が色濃く表れたテキストでもある。物理学的な宇宙の誕生(ビッグバン)と、ひとりの人間が抱く感情(生きる喜び)の発露。こうしたマクロなスケールとミクロなスケールを直結させる想像力を象徴的に表していたのが、『AIR』のオープニングムービーで真っ白な背景に表示される「the 1000th summer――」という一文だった。
「作中時間の飛躍」と「会話における論理の飛躍」は、どちらも「中間プロセスの無効化」という点において同質の機能を果たしている。かつてPCノベルゲームにおいて、限られたリソースの中で物語を紡ぐために発明された「時間のショートカット」という技法は、麻枝によって独特の論理構造を備えた文体へと昇華されたのである。
そしてこの文体は、「終わりの見えない」スマートフォンゲームのプレイ体験に亀裂をもたらすものとして機能する。スマートフォンゲームというメディアは、作品世界では一刻の猶予もない危機的な状況が続いているはずなのに、利益を上げ続けている限りは運営が続き、幕間のサブストーリーが無限に追加されていくという矛盾を根本的に抱えている。
その構造自体は容易には打破しえないものだとしても、麻枝のテキストが持つ独特の文体は、いずれ唐突に訪れる「世界の終わり」に直面した際の感覚を、プレイヤーに予感させるものとして機能しているとも言えるのではないだろうか。それは現実を支配する資本の運動に対する、創作による抵抗の優れた一例としても捉えられる。
「生成」を「作品」にするもの
最後に取り上げたいのが、「生成AIによる作品に人間は感動することができるか」という現代的な論点の扱い方である。
AIによる無限のシミュレーションの中で、たった一度だけイレギュラーが発生したというのが、今回のイベントのクライマックスとなっている。そのイレギュラーとは、気丈な先輩兵士として振る舞っていたAI白河ユイナが孤独な繰り返しに耐え切れず、茅森の前で涙を流してしまうというものだ。そのAI白河ユイナを慰めるために茅森が曲を作ることになり、作中バンド・She is Legendの新曲「Moon Day Real Escape」として演奏される。
しかしここで注意すべきは、この曲を作った「茅森月歌」も、AI自身が演算した再現データに過ぎないということだ。つまり、この「Moon Day Real Escape」という楽曲は、AIが「茅森月歌ならこう歌うだろう」と演算して出力した生成物に他ならない。
イベントはAI白河ユイナが、「月歌…ここでのお前とはこれでお別れだが、この曲の再生だけは無断でも許してくれ。/魂なんてものはないが、刻んでおくから…記録媒体に。/ずっとずっと大切にするから…例え古びて擦り切れて、お前の姿が滲もうとも…。/それを再生することが…宇宙が終焉するまでの何千億年の唯一の…。/生きる喜びだ。」という言葉を吐露して終わる。
AI白河ユイナが涙を流すスチルが入り、感動的なクライマックスが演出される。しかし、宇宙が終わりを迎えるその日まで、AIの孤独なシミュレーションが続くであろうことを、プレイヤーは知っている。

私たちは「Moon Day Real Escape」の音源を、ゲームの画面から離れ、任意のストリーミングサービスを使って単体の音楽作品として聴くことができる。それを聴いて心を動かされる経験は、ひとりシミュレーションの中に置き去りにされるAI白河ユイナに感情移入する経験なのか? いや、実際にはAIが生成した曲ではなく、麻枝准という人間によって作られた曲であり、その旋律に心を動かされているだけで、それは「AIに感情移入する」こととは異なるのではないか?
そもそも、設定上She is Legendのソングライターは茅森月歌というキャラクターであり、麻枝准ではない。「作中バンドの曲として作られた曲を聴く」という経験において、現実世界でスピーカーから流れる音の震えの鑑賞と、虚構のキャラクターの感情にシンクロすることは重なっている。ヒト・ナービィに関するそれと同じく、何が「本物」で何が「偽物」であるかという問いは宙吊りにされる。この観点からすれば、AIが作った曲なのかどうかという問いは、そもそも問いとして立てる必要がないとも言えるだろう。重要なのは、「その曲を聴いて、とにかく私の心は震えた」という事実のみである。
とはいえ、本イベントのAIには、現実のAI技術と照らし合わせて明確にフィクショナルな点がひとつある。白河ユイナという仮想人格を生み出したこのAIは、いずれ必ず訪れる宇宙の「終わり」を前提に、そこに至るまでの慰めとして音楽を必要としたという点だ。詳しい説明は省くが、現実の生成AIは、入力された情報の意味を「高次元空間上の位置関係」として一挙に捉える。インターフェース上の出力は一文字ずつ行われるとしても、その背後にある意味の演算に、私たちが感じるような「時間の流れ」は存在しない。無時間的であるがゆえに、そこには「終わり」の概念もない。
私たちが「Moon Day Real Escape」に心を動かされるのは、大前提としてこの曲がAIではなく、麻枝准という生きた人間によって紡がれたからである。しかし、単なる演算システムであるはずのAIが人間的な「死」や「終わり」を希求し、その瞬間にのみ宿る輝きを垣間見たという、フィクショナルな感動もそこには重なっている。
麻枝准は本イベントのシナリオを通じて、「AIが生成した作品にも感動することは可能か」という問いに対し、「「終わり」を望むAI」という虚構をぶつけることで、逆説的に「作品の感動には「終わり」が不可欠である」ことを浮かび上がらせているのである。これは音楽とシナリオをともに自ら手がける、麻枝准というクリエイターにしかできないアプローチだと言えるだろう。
幾千億年先から見た「今」という光
スマートフォンゲームにおいてプレイヤーは、二重の意味で「終わりの見えない」戦いを強いられる。作品としての「終わり」は見えないのに、常にコミットし続けなければ、サービス終了という形で突然「終わってしまう」かもしれないのだ。私たちは明日も明後日も、ログインボーナスを受け取り、セラフ部隊員たちとともに朝を迎えることができると信じている(あるいは、信じざるをえない)。
麻枝准は3周年という記念すべきタイミングで、この構造に鋭い楔を打ち込んだ。麻枝が今回のイベントで描いたのは、プレイヤーが愛するキャラクターたちも、彼女たちがキャンサーから守り抜こうとする世界そのものも、宇宙の死という絶対的な「終わり」の前では、確実に消滅するという事実である。
だが、そのあまりに直截的な「終わり」のイメージの提示こそが、『ヘブバン』というスマートフォンゲームを単なる暇つぶしのコンテンツから、切実な「生」の物語へとまた一段引き上げたのではないだろうか。
AI白河ユイナが永遠に近いシミュレーションの果てに見出したのは、統計的なデータの集積ではなく、かつて作中世界に実在した「茅森月歌」という、かけがえのない「光」の輝きだった。それはすべてのプレイヤーにいずれ訪れる、「いつかこのゲームのサービスが終了し、データの消滅とともに作中世界もすべて消え去る時が来る」という未来を先取りしたもののように思われる。
確かに『ヘブバン』というゲームに「終わり」は見えないかもしれないが、テキストを読んでいる私たちの感動は、間違いなく「今」この瞬間に生じている。一見してアクロバティックな構造を持つ本イベントのメッセージは、実のところ極めてシンプルなものだと言えるだろう。「終わりの見えなさ」と「いつ終わってもおかしくない」という予感との狭間で、「今」画面上で展開される物語に涙し、音楽に心を震わせること。いずれにせよ死という絶対的な「終わり」を迎えるのであれば、その感動を思いきり享受すべきなのだ、と。

