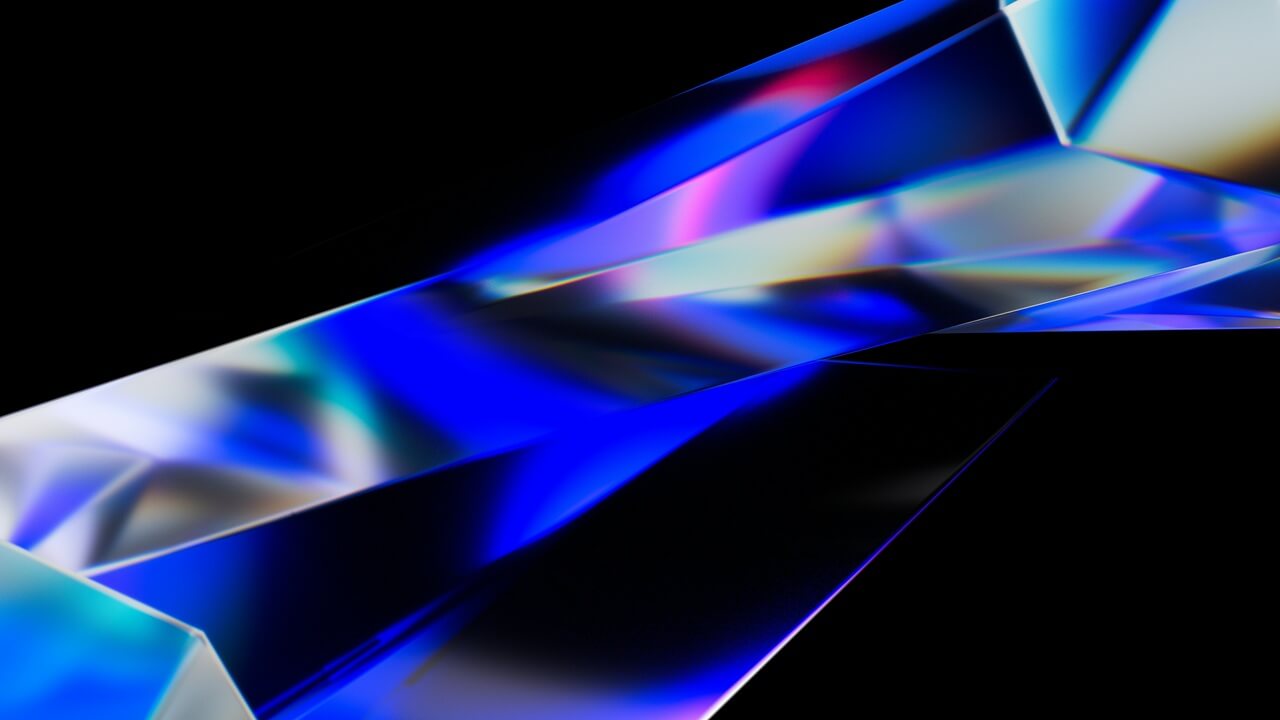不透明なフィルターとしての具体詩——AIによる「透明性の擬態」を解体する視座
北出栞
インターフェースが作り出す「他者性の幻想」
AIが出力するテキストは、文法的にも意味的にも破綻がなく、あたかも人間に語りかけられているかのように滑らかである。しかし、その滑らかな表層の向こう側で行われているのは、私たちの直観とはかけ離れた数学的な演算である。「王 – 男 + 女 = 女王」という有名な例に象徴されるように、AIの内部において言葉は「意味」ではなく、高次元空間上の座標を持つ「トークン(数値化された言葉の単位)」として処理されているのだ。
対話型AIのインターフェースは、この「言葉を離散的な数値表現として扱っている」という事実を隠蔽することに特化している。ユーザーに対して言葉を「透明な意味の乗り物」として提示し、あたかも意思を持った他者がそこにいるかのような錯覚……「他者性の幻想」を生み出す設計が徹底的になされているのである。
意味の擬態 vs 意味の還元
この幻想に抵抗するための参照点として、北園克衛に代表される20世紀前半の具体詩(コンクリート・ポエトリー)の試みを再考したい。彼らの作品とAIは、同じ「言葉」を素材としながらも、その扱い方は真逆なものとなっている。
- AI: 出発点は「不透明な演算(ブラックボックス)」である。内部では数値の確率計算を行っているにもかかわらず、出力段階ではそれを隠蔽し、「言葉の透明性(自然な意味伝達)」を擬態する。
- 具体詩: 出発点は「透明な意味(日常言語)」である。彼らは言葉から意味伝達という機能を剥ぎ取り、インクと余白からなる幾何学的な配置として提示することで、「言葉の不透明性(記号としての物質性)」へと還元する。
AIのインターフェースは、統計的に生成されたトークンの連なりを、上から下へと流れるタイムライン上で表現することで、「論理の整合性」や「時間の流れ」を演出する。具体詩が試みたのは、そうした線形性の解体だった。
北園は「一つの思想があり、それを表現するために詩の形式があり、その詩の形式をつくるために修辞術があり、最後にそれを操つるところの詩人がある」といった従来の詩のあり方を否定した。彼の詩作品においては、「言葉は単にポエジイ(詩的想像)のオブジェ(物象)にすぎない」。数学者ミンコフスキーの次の言葉に共感を示したのも示唆的である。「今後は空間それ自体とか、時間それ自体などというものは単なる影として消え去る運命にあるのだ。ただこれら二つのものの一種の結合だけが、一個の独立した実在を維持していくことになるだろう」。北園は言葉が時間(意味の流れ)と空間(物理的実体)の両方にまたがる素材であることを明らかにするために、時間的な「意味の流れ」をあえて解体し、空間的な「オブジェ」として再提示したのである。
この試みは、現在のAIのあり方を逆照射している。AIは内部の演算においては、文脈全体を並列的に捉える「空間的」な処理を行っている。しかし出力されるテキストは、その空間性を隠蔽し、人間にとって自然な「線形的な時間の流れ(タイムライン)」へと押し込められたものだ。具体詩は、AIがインターフェースの裏側に隠したこの「空間性」を、アナログな手法で先取りして暴き出していたと言えるのである。
※北園の言葉(ミンコフスキーの引用含む)はすべて、「前衛詩論」(『2角形の詩論 北園克衛エッセイズ』リブロポート、1987年)より。
高次元空間の「翻訳」としてのレイアウト
私たちがAIの本質を正しく掴むためには、本来であればAIと同じように言葉をベクトル(計算対象)として捉え、その演算プロセスを脳内でシミュレートすべきである。言葉の意味に惑わされず、トークン同士の確率的な結合としてテキストを認識すること。それができれば、AIによる「透明性の擬態」を見破ることは容易いはずだ。
しかし、人間の認知能力には限界がある。私たちは数百、数千次元のベクトル空間で起きている演算を、直感的にイメージすることはできない。ここで、具体詩の手法が、人間とAIの間を橋渡しする補助線として浮上する。
もちろん、数千次元の数学的な距離と、紙の上の二次元的な距離は等価ではない。二次元平面への翻訳は、必然的に高次元の複雑な情報を欠落させる。
つまりこの配置は、数学的に正確な「ベクトル演算の図解」ではない。しかし、AIのインターフェースが強制する、「意味の流れ」を読むモードでの言葉との向き合い方を中断するための補助具としては機能する。
言葉と言葉を物理的に引き離したり、サイズを変えて並べたりといった「レイアウト」という行為は、言葉を「意味」から引き離し、再び「記号」へと還元する側面を持つプロセスだ。具体詩の制作は、人間には知覚不可能な高次元の計算構造を、私たちが扱うことのできる視覚情報へと漸近させる試みとして再解釈できるのである。
AIの言葉に対する「半透明」な視座
AIによって生成された言葉の羅列を前にしたとき、私たちはそれを単なる文章として読むだけでなく、「本来そこにあるはずの計算構造」を透かし見るよう努める必要がある。
AIの内部構造は「意味的な距離(ベクトル間の類似度)」で構成されているのに対し、具体詩が紙面上で行う配置は、あくまで二次元平面上における「物理的な距離」であり、数学的にはまったくの別物だ。しかし、線形性を拒絶し、言葉を記号として捉えるという一点において、両者は共振する。
「物質的な不透明性」をフィルターとして挿し挟むことで、一見滑らかな言葉の奥にある不可視の計算空間を、物理的な実在として擬似的にイメージする……こうした、言葉の意味(透明性)を追いつつも、その計算構造や物質性(不透明性)を決して見失わない視座を、ここでは「半透明」な視座として定式化したい。それは意味のレイヤーと物理のレイヤーを重ね合わせ、その双方を絶えず往還する能動的な知覚のあり方である。
「演算」の近似としての「編集」
「半透明」な視座を得るために具体的なアクションとして必要になるのは、言葉に対する物理的な干渉――配置換え、分断、コラージュ――を通じて、AIを介した言葉との関わり方を「対話」から「造形」へとシフトさせることだ。
画面上のテキストをコピー&ペーストし、改行を入れ、フォントを変え、余白を作るといった「編集」のプロセス。それは、AI内部の「高次元ベクトル空間」における確率的な記号の結合を、知覚可能な「物理的な二次元空間」へと近似的に落とし込む実践である。
私たちはAIが出力する流暢な言葉を一度「冷たい記号の塊」として突き放し、自らの手で再構築しなければならない。言葉が意味の伝達手段であると同時に、操作可能な空間的オブジェクトでもあるという認識を持つこと。それこそが、ブラックボックス化したこの新しいテクノロジーと向き合うために必要な、批評的認識であるはずだ。